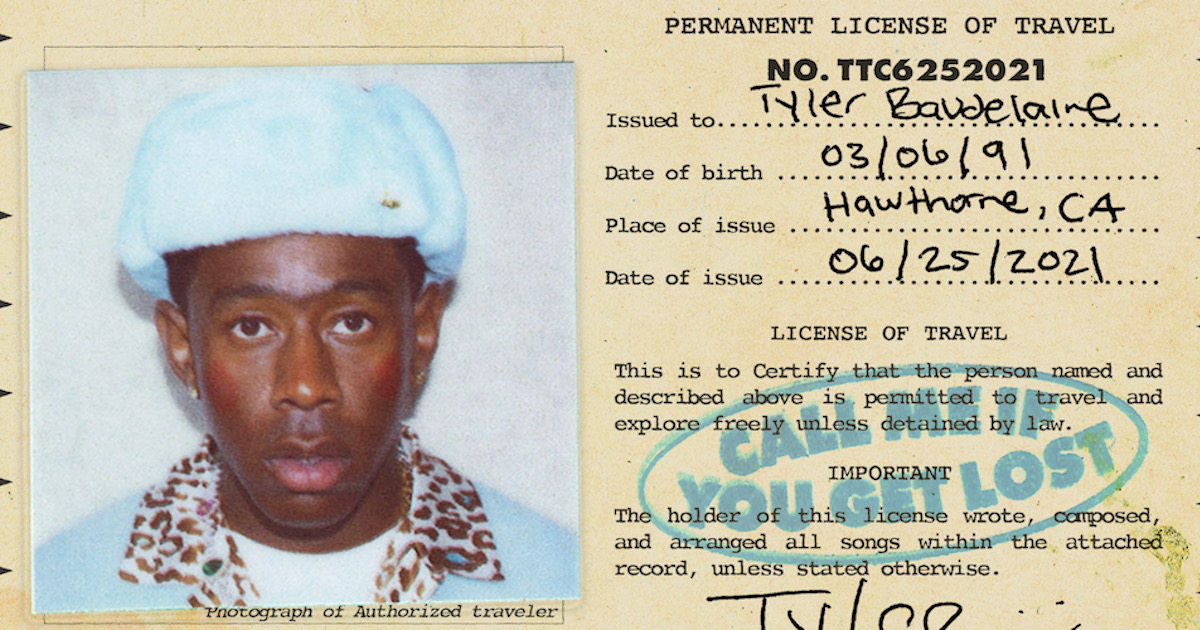text: Sho Okuda
格闘技は国境を越える—私がそう肌で感じたのは、2011年、学生時代にタイを旅行した時のことだった。その旅行の3年前からキックボクシングのジムに通っていた私は、アマチュア9戦6勝3敗(当時)という微妙な戦績を引っさげて、バンコクにあるムエタイのジムに足を運んだ。タイ語を解さぬ私は、拙い英語でジムのトレーナー陣とコミュニケーションを取り、初めての海外一人旅で、英語が国境を越えることを体感した。だが、その時それ以上に強く印象に残ったのは、格闘技もまた国境を越えるということであった。トレーナーが両方のミットを胸の前に構えれば、それはミドルキックの指示だと理解できたし、バンデージを外すよう指示されれば、これから首相撲が始まるのだと分かり、首相撲が苦手な私は憂鬱になった。私が練習に赴いたそのジムは、欧米からのバックパッカーが冷やかしに来るようなところであったが、トレーナー陣は元ランカーを含む強豪ぞろい。レンチュンと呼ばれる、グローブを着けずに行う軽めのスパーリングでは、私が日本で覚えたフェイントの数々をことごとく見破られ、その技術も世界共通のものなのだということを、ケチョンケチョンにされながら思い知らされた。
3年遡り、私がキックボクシング・ジムに入会した頃の話をしよう。練習中にジムでかかっていたBGMは、だいたいいつもヒップホップだった。当時チャートを席巻していたのはリル・ウェイン(Lil Wayne)やT.I.、カニエ・ウェスト(Kanye West)、ドレイク(Drake)あたりだろうか。練習中にそれとなく耳にしていたヒップホップは、BGMとして機能するばかりでなく、知らず識らずのうちに私をエンパワーしていた。例えば「Live Your Life」が流れていると、T.I.のモチベーショナルなラップに合わせてパンチを打つことで、サンドバッグの30秒連打も幾分か楽に感じられた。それはきわめて肉体的な経験だった。そのヒップホップが、格闘技と同じかそれ以上に国境を越えて世界中に広まっていることは、言うまでもないであろう。あれから10年経った今、本稿執筆時点(2018/9/17)でのSpotifyの公式プレイリスト「トップ50(グローバル)」にも、カニエとリル・パンプ(Lil Pump)の「I Love It」を筆頭に多数のヒップホップ楽曲が含まれている。
そんな、世界中に広まっている格闘技とヒップホップは、相思相愛の関係にあるといっていい。かねてよりラップのリリックには格闘家の名前がしばしば登場していた。ドクター・ドレー(Dr. Dre)の「Nuthin’ But a ‘G’ Thang」では、スヌープ・ドッグ(Snoop Dogg)が「それは『本物(Real Deal)』のホリフィールドよりもリアルなんだ」と、元ヘビー級王者のイベンダー・ホリフィールドの名前をリリックに忍ばせていたし、自らもボクシング経験者である50セント(50 Cent)は「Many Men (Wish Death)」で「全盛期の(モハメド・)アリ」を自称していた。ジョー・バドゥン(Joe Budden)は「Get No Younger」で、UFCファイターであるチャック・リデルとクイントン・“ランペイジ”・ジャクソンの2名に言及している。また、“Money”の異名を持つフロイド・メイウェザーは、リル・ウェインやドレイク、ニッキー・ミナージュ(Nicki Minaj)といったYoung Moneyのラッパーたちと親交が深い。元ボクシング王者のエイドリアン・ブローナーは、WBCライト級タイトルマッチで、ケンドリック・ラマー(Kendrick Lamar)が生で「Backseat Freestyle」をパフォームするなか入場し、見事なTKO勝利でベルトを巻いた。
こうした両者の「相思相愛」の背景には、様々な共通点がある。まず、どちらも「やる側」に回ってみると意外に難しい。ボクシングやキックボクシングの1ラウンドは3分だが、ミット打ちを経験すると、この3分がいかに長いかを思い知らされる。ヒップホップも同様である。ラッパーたちが飄々とヴァースを蹴るのに憧れて自分もラップしてみると、韻を踏みつつ耳に心地よいフロウを実現するのがどれだけ難しいかが分かる。これはDJやビートメイキングでも同じことだろう。一定レベルの技量を身につけるには、それなりの年月を要する。それでも、理想の動きを試合で実現して勝利を収めたとき・満足のいくラップをビートに乗せられたときの快感は、何にも代えがたいものである。過激化するラップ・ゲームは、格闘技の試合と同様に危険と隣合せであるが、ビーフがスカッシュされれば互いを笑顔で認め合うという点も、格闘技と似通っている。そして、「観る側」「聴く側」に回ると、彼らの闘う姿に、音と言葉に、勇気づけられる。元K-1王者の魔裟斗氏は、格闘技は究極的には「自己満足」だと語っていた[1]が、その他ならぬ「自己満足」が観る者・聴く者をインスパイアするという点でも、格闘技とヒップホップは共通しているといえるだろう。
リングやオクタゴンに上がれば、出自は関係ない。そこには自分と対戦相手とレフェリーの3者がいるだけであり、ゴングやブザーが鳴れば、あとは自らの強さを拳で証明するだけである。ヒップホップも同様だ。歌唱や楽器の演奏を学ぶ機会を持たぬ若者も、DJやラップやダンスやグラフィティを通じ、自らの実力を証明(Show & Prove)することで居場所を作ってきた。そうした彼らの姿に人々がインスパイアされ続けてきて、今のヒップホップ人気がある。こうした、格闘技とヒップホップに共通する要素を見事に表現したCMを最後に紹介したい。アイルランドの総合格闘家コナー・マクレガーが、先述したメイウェザーにボクシング・ルールで挑戦した際に制作された、Beats by Dreの広告である。
https://youtu.be/nRKeamyoTsQ
同CM内では、Beats by Dreの代表いわく「コナーと同じファイティング・スピリットを持つ」[2]リアムという少年が、友人とふざけ合いながら「俺は世界の王になるんだ」「(チャンピオンになったら)豪邸に住むさ」などと口走っている。同じダブリン出身のマクレガーがバンデージを巻きながら聴いているのが、ザ・ノトーリアス・B.I.G.(The Notorious B.I.G.)が自らの成り上がるストーリーを描いた「Juicy」である。荒廃した団地に住むリアム少年らが通りすがりの警察に目をつけられる様子も、「ビッグになっても俺らと遊んでくれる?」「もちろんさ」という会話も、同曲のリリックと重なる。リアム少年はマクレガーがそうしたように、またビギーがそうしたように、何も無いところから、己の拳で道を切り拓こうとしているのだ。そして、その姿はいずれ、多くの人々を勇気づけることとなるはずだ。このアティチュードはきわめて格闘技的であり、同時にきわめてヒップホップだ。格闘技とヒップホップはそれぞれに、また互いにリンクしながら、今後も観る者・聴く者をインスパイアし続けていくにちがいない。